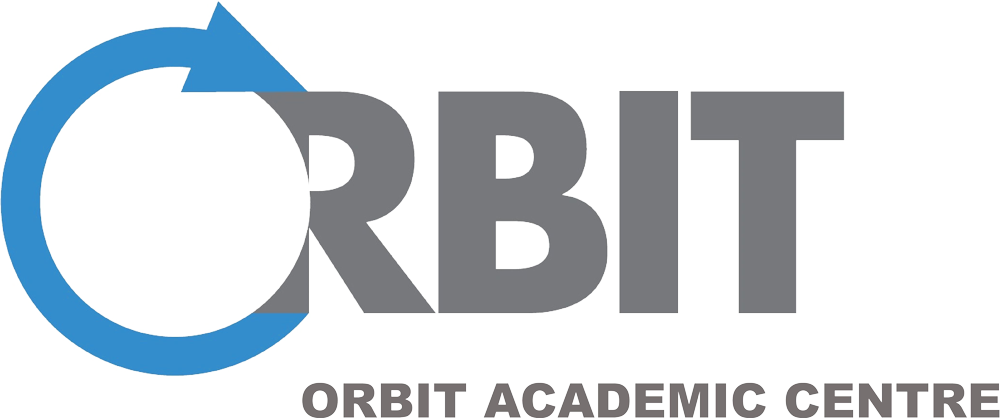分野・教科・言語の壁を飛び越えて
2024.09.06
オービットの「グローバル理数クラス」では前期のまとめとして、生徒ひとりひとりにプレゼンテーションをしてもらいました。テーマは、「好きな動物について」です。本コラムでは、準備期間も含めたプレゼンテーションの様子をふまえて、生徒たちの今後の学びと成長にどう繋げていくか、いくつかの観点からお話しできればと思います。
①興味関心に基づいた、主体性のある学習へ
中学生は、ちょうど子どもと大人の中間にいます。学習の面でも、幼児期から小学生にかけて感じた不思議や憧れをモチベーションとして保持したまま、すこしずつアカデミックな態度を身につけていく時期です。今回も生徒たちは、生きものに対して幼いときに感じた「強い」「大きい」「危ない」というようなワクワクに対して、それを説明する言葉や概念を知ったり、その理由を論理的に考えたりするということを準備の過程で行ってくれました。そのプレゼンテーションのなかには、今後の主体的・発展的な学習につながる以下のような視点も感じられました。
(1)分類学的視点
たくさんの物事をある特徴に基づいて分類することは、学問の古典的な態度のひとつです。たとえば今回は、gecko(ヤモリ)はreptile(爬虫類)なのに、newt(イモリ)はamphibian(両生類)である「紛らわしさ」について、これは日本語での音がたまたま似ているだけで、分類学上このふたつは別の生物である、ということを確認したりしました。ちなみにこれに関しては、イモリは漢字では「井守」と書くので、井戸の近くに住んでいるから両生類、という覚え方があります。
(2)化学的・生物学的視点
たとえばそのヤモリですが、実はフグと同じtetrodotoxin(テトロドトキシン)と呼ばれる毒を持っています。このテトロドトキシンはalkaloid(アルカロイド)とよばれる有機化合物の一種ですから高校化学の範疇ですし、またこの毒はナトリウムチャネルを阻害することで人体に麻痺を起こさせますが、これは高校生物で学習します。こんなことをいうと中学1年生の生徒たちにとっては先のことに感じられるかもしれませんが、興味をもって学べばすぐに到達できる内容でもあります。
以上はプレゼンテーションから私が感じた今後の学習の方向性ですが、もちろん、これが科学以外の分野に転じていくこともありえると思います。たとえば、毒性をもつ生物の売買や流通に関する法整備はどうなっているか(フグを食べることを史上最初に禁じたのは豊臣秀吉といわれています)など。いずれにせよ、理科の学習を通して経験してほしいのは、生物そのものへの興味もそうですが、科目や分野の垣根を越えて物事を学んだり論じたりすることの面白さです。
②プレゼンテーションの創意工夫
今回は本番一週間前の時点で、中間発表を実施しました。そこでは内容のチェックもしましたが、発表の仕方についても意識してもらいました。仮に同じ内容であっても、違う言い方をしたり、情報を出す順番を変えたり、聴衆に問いかけるなどの手法を取り入れることで、よりわかりやすく、より興味を惹くものにできます。プレゼンテーションの上手さが評価される機会も増えている昨今、当初は「プレゼンテーションをなるべく効果的なものにする」という視点をそもそも持っていなかった生徒たちも、中間発表を経て、そのためのいろいろな工夫を考えるきっかけになったようです。
③英語による学習と発表の経験
言うまでもなく、現代のLingua Franca(リンガフランカ―学術や商業において共通の母語を持たない人達の間で意思伝達手段として使われる言語)は英語です。インプットであってもアウトプットであっても、それらを日本語ではなく英語で行うことのメリットははかり知れません。より多くの情報や意見をスムーズに得ることができますし、より多くの人に自分の成果を知ってもらうこともできます。リテラシーの高い生徒にとっては、ChatGPTに日本語ではなく英語で質問したほうが、質量ともに圧倒的によい返答が得られるということが、既に当たり前のことになっています。
これからの時代は、教科書や論文が英語で書かれていても臆さず正確に読み書きできる能力や、論理的思考力と表現力、何より教科や言語の壁を飛び越えて自由に考えることを楽しめる態度を育むことが、必須の学びの形態と言えるでしょう。
(グローバル理数クラス担当 算数・数学科 東)