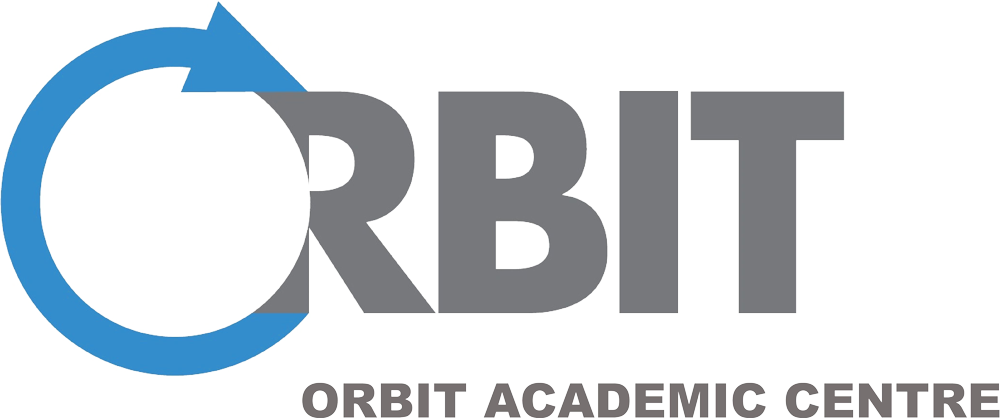須崎 優未子 さん
「来星したことで拓けた進路 ~日本の私立中から海外大学へ~」
(2025.6.25付)
- 来星の経緯とオービットとの出会い
高校1年次にシンガポールへ渡航しました。それまで通っていたカリタス女子中学校では、総合学習や探究活動、奉仕活動などが充実しており、学びの幅広さに魅力を感じていました。コロナ禍が明け、待ちに待った部活動も再開される中で、突然のシンガポール移住には正直なところ前向きになれずにいました。ただ、カリタスの校長先生から「高2の夏までなら帰国しても復学できる」との言葉をいただき、当初は1年間のみの滞在を予定していました。
しかし、インターナショナルスクールでの学びを通じて、言語面・学習面ともに自分の可能性を再認識することができました。もちろん困難もありましたが、試行錯誤を重ねることで乗り越えられた経験は、大きな自信につながりました。その過程でIBDPを取得するかどうかを真剣に考えるようになり、英語力の強化とTOEFLスコアの向上が必要だと判断し、母の勧めでオービットへの通塾を決めました。
- オービットで得た学びと成長
オービットでは主に英語を受講しました。当初TOEFLで70台だったスコアが最終的には104まで伸び、着実な成果を実感しました。特にWritingにおいて、文法学習だけではなく論理展開や文章構成の技術を学びました。これは学校のエッセイや将来的なアカデミックライティングにも応用可能な、汎用性の高い知識だと感じています。また、SpeakingやWritingの授業では、他の生徒の視点や発想に触れることで、自分の思考の幅が広がりました。集団授業ならではの知的刺激が得られたと思います。
さらに、英語以外でも様々な指導を受ける機会がありました。例えば、数学では学校の授業よりも高度な指導を受けることができ、学校の内容がむしろ容易に感じられるようになりました。また、ちょっとしたアドバイスを受けることも多々あり、例えば生物の専門用語は英語のまま覚える方が効率的で、日本語に訳すと理解が遠回りになるという指摘は非常に実践的でした。
進路に関する情報も豊富で、日本の大学や学部の選び方、IBやTOEFLのスコア目安など、具体的な相談に乗っていただけたことも大きな支えとなりました。卒業後も受験プランに関して個別相談をしてもらえたことは嬉しく思っています。
- 海外大学(NUS)という選択
海外大学を志望した理由は、常に新しい挑戦を求めていたからです。日本人が少ない環境で、すべての専門科目を英語で学ぶというのは、私にとって大きな挑戦であり、成長の機会でもあります。インターナショナルスクールでの経験を通じて、語学力や国際的な視点だけでなく、精神的にも大きく鍛えられました。海外大学への進学は、そうした成長をさらに継続させるための選択です。
また、グローバル化が進む社会でビジネスを学ぶには、海外ならではの視座が不可欠だと感じています。中でもNUSを選んだのは、シンガポールがアジアのビジネスハブであり、多国籍企業やスタートアップに近い環境に魅力を感じたからです。また、安全性や暮らしやすさも魅力の一つです。加えて、NUSのビジネス学部は国際的評価が高く、実践的な学びと広範なネットワークを得られる点にも強く惹かれました。
- ビジネスを学部として選んだ理由
私がビジネスを選んだ理由は、「論理」と「創造」の両面を探究できる分野だからです。数学のような論理的思考と、新しいアイデアを生み出す創造的な活動の両方に魅力を感じており、特にマーケティングはその融合が可能な学問だと考えています。
また、IB Businessで企業戦略や市場分析を学ぶ中で、ビジネスが単なる利益追求にとどまらず、社会貢献や持続可能性にも深く関わることを知りました。そこから、将来はビジネスを通じて社会に良い影響を与えたいという思いが芽生えました。
そして、ビジネスは資本主義社会における“共通言語”とも言える存在であり、あらゆる分野と接点を持ちます。私は幅広い分野に関心を持つタイプなので、ビジネスを学ぶことで多様な領域に関わり、柔軟に貢献できる可能性がある点にも強く惹かれました。
- IB学習における工夫と戦略
IBカリキュラムでは、限られた時間の中でいかに効率的に学習を進めるかが鍵となります。私自身は、自分に合った学習法を模索し、実践することを重視しました。
例えば、時間的制約が厳しい中、手書きのノート作成では限界を感じるようになり、教科書の内容をChatGPTに要約してもらうなど、AIの力を状況に応じて活用しました。こうした工夫が、学習効率の向上につながったと感じています。
その他にも、IBファイナルのパストペーパー(過去問)を繰り返し解くことで、インプットとアウトプットを自然に繰り返し、知識の定着を図りました。また、Quizletを活用し、自作の問題を作成して、語彙の定義を答える形式で記憶を強化しました。
- インター校で成果を上げる秘訣
インター校で成果を上げるためには、授業への主体的な参加と、先生たちとの良好な関係構築が不可欠です。授業を丁寧に聞くことで先生との信頼関係が築ければ、IBのファイナルに向けた過去問の添削など、学習面での支援も多く得られます。
また、スケジュール管理も極めて重要で、課題提出をギリギリまで遅らせることは避けるべきです。計画的な取り組みが、学習の質を大きく左右します。
最後に、私たちのように英語が第一言語ではない生徒は、ネイティブの倍以上の努力が必要だと感じています。大変なことも多いと思いますが、皆さん頑張ってください。
※編集者注:上記の文章は生徒へのインタビューをもとにオービットがまとめました。